不動産知識
成年後見制度の“盲点”と上手な付き合い方
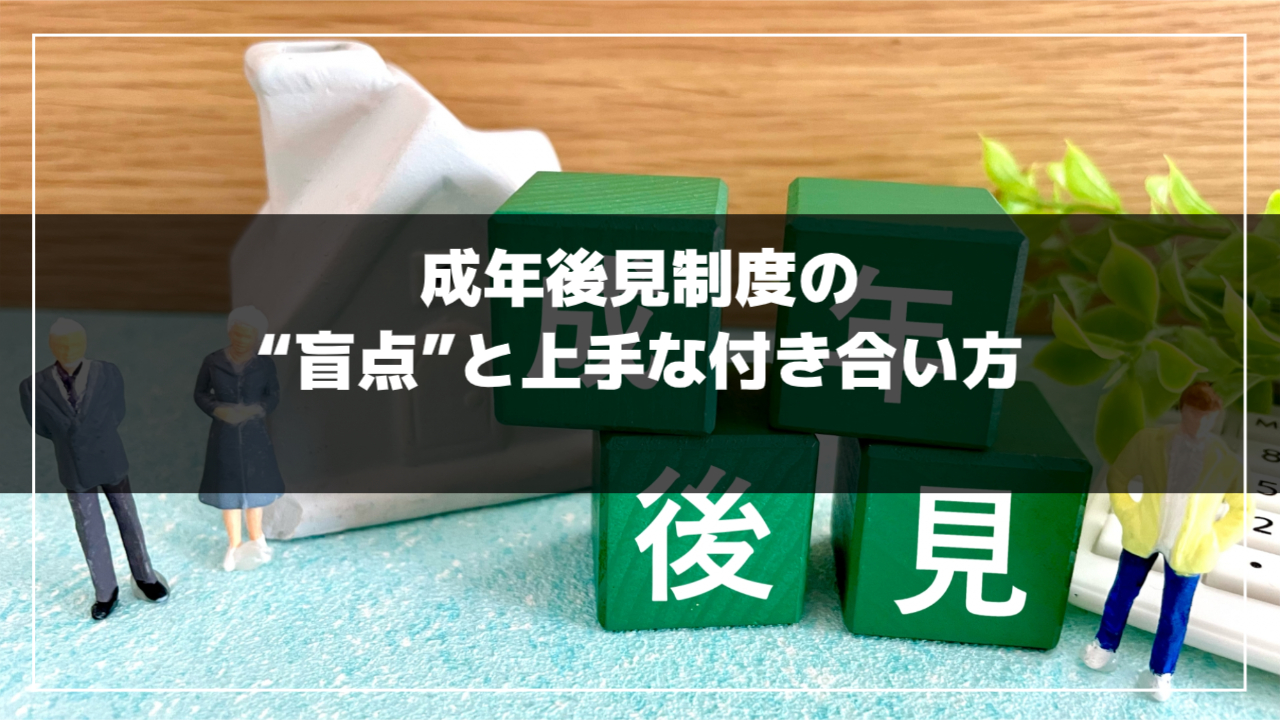
ご家族が意思表示や財産管理を一人で行うのが難しくなったとき、成年後見制度は心強い味方です。
ところが、制度の仕組みや後見人の選び方を十分に理解しないまま進めると、手続きが停滞したり、家族の希望とちがう方向に進んだりする“盲点”が生まれます。
この記事では、実務の現場で見えてくるリスクと、トラブルを避けるための具体策をわかりやすくご紹介します。
成年後見制度の基本
- 目的:本人に代わって法律行為や財産管理を行い、生活を守ること
- 権限:日常の支払い・口座管理・契約・財産処分など
※重要な財産処分には原則として家庭裁判所の許可が必要です - キモ:後見人の力量・姿勢・連絡体制が、そのままご家族の安心につながります
現場で見える“盲点”
1.コミュニケーション不足
連絡がとりづらい、報告が少ないといった状況では、意思決定が後ろ倒しに。
特に不動産の売却や活用など、タイミングが重要な案件では大きな影響
2.後見人選任後の“解任の難しさ”
後見人が違法行為をしない限り、解任は容易ではありません。
最初の選任が事実上の“決定打”となることを意識する必要があります。
3.専門職の体制差
単独事務所で後見を専業的に受任している場合、事務量や収益構造の都合で利害調整が難航することも。
一方で、登記業務など本業が多忙な事務所では、連絡体制が不明確だと対応遅延の温床になり得ます。
4.手数料・報酬をめぐる温度差
売買などが絡むと、報酬見込みや役割範囲の認識にズレが生じることがあります。
事前の「見える化」が不可欠です。
実例から学ぶポイント
共有不動産の売却で、家族と合意し、後見人を通じて裁判所許可申請へ。しかしその後、手続きが滞り“妨害”に近い対応で大幅に遅延。最終的には家族が同席し丁寧に意思を伝えることで成立したが、最初の選任と、連絡体制・報酬認識のすり合わせ不足が影響していた。
トラブルを避けるための「事前チェックリスト」
後見人選任前に、以下の点を家族で確認しておきましょう。家族会議用メモとしても活用できます。
- 目的の明文化
例:「居宅以外の不動産を○月までに売却検討」「介護費用の支払い安定化」など、期限と優先順位を書面で明記 - 連絡・報告ルールの合意
月次報告の方法(メール/書面/面談)、緊急時の連絡先、レスポンスの目安などを合意 - 費用と報酬の可視化
月次の管理手数料、臨時対応の追加費用、売買等の成果報酬の有無を見積書形式で確認 - 体制の確認
担当者のバックアップ体制、長期不在時の代替対応、事務所の基本対応時間など - 不動産対応の姿勢
査定取得の件数、相見積もりの可否、裁判所許可取得の想定スケジュール - 家族以外の第三者の同席
福祉関係者や信頼できる第三者の同席も検討材料に
もし、すでに滞りを感じたら
- 記録を残す:連絡日時・要件・回答を時系列でメモ。
- 合意事項を再確認:初期目的・報告頻度・費用の文面を相手と共有し直す。
- 家庭裁判所へ相談:手続き停滞や不透明さが続く場合、早めに状況を相談。
- 専門家のセカンドオピニオン:社会福祉士、弁護士、司法書士など別ルートでアドバイスを受ける。
まとめ
成年後見制度は、ご家族の生活と財産を守るための大切な仕組みです。
最大のリスクは「選任前の準備不足」と「連絡の希薄さ」。
だからこそ、目的の書面化・連絡ルール・費用の可視化を“最初に”整えることが、
後の安心とスムーズな意思決定につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な案件については、必ず所管の家庭裁判所や専門家にご相談ください。

